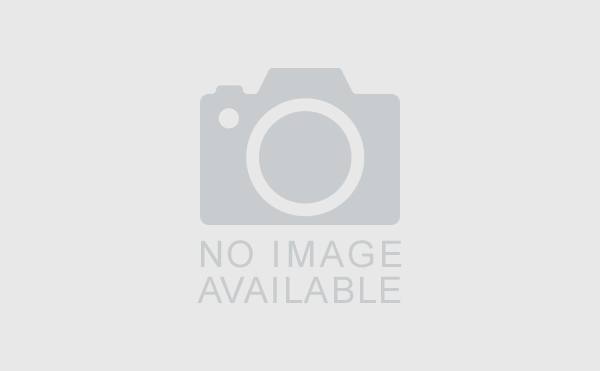座談会御書「転重軽受法門」2025年(令和7年)8月度
〈御 書〉
御書新版1356㌻3行目~5行目
御書全集1000㌻3行目~4行目
〈本 文〉
涅槃経に「転重軽受」と申す法門あり。先業の重き今生につきずして、未来に地獄の苦を受くべきが、今生にかかる重苦に値い候へば、地獄の苦みぱつときへて、死に候へば人天・三乗・一乗の益をうる事の候。
〈現代語訳〉
涅槃経に「転重軽受」(重きを転じて軽く受く)という法門がある。
過去世でつくった宿業が重くて、現在の一生では消し尽くせず、未来世に地獄の苦しみを受けるはずであったものが、今世において、このような(法華経ゆえの大難)重い苦しみにあったので、地獄の苦しみもたちまちに消えて、死んだ時には、人・天の利益(りやく)、声聞・縁覚・菩薩の三乗の利益、そして一仏乗(いちぶつじょう)の利益(りやく)たる成仏の功徳を得るのです。
〈背 景〉
文永8年9月12日に「竜の口の法難」に遭われた大聖人は、佐渡へ流罪される間、相模国依(さがみのくにえ)智(ち)の本(ほん)間(ま)六郎左衛門尉(さえもんじょう)の座敷へ預けられました。そこへ3人か、又はそのうちの代表の1人がお見舞いを申し上げた事に対する御返事です。
〈講 義〉
本抄は、文永8年10月5日、大田左衛門尉(おおたさえもんじょう)・曾(そ)谷(や)入道(にゅうどう)・金原法(かなばらほっ)橋(きょう)に宛てたお手紙です。
3人の人物像は、下総国(現在の千葉県北部などの地域)で住んでいた門下で、大田左衛門尉は富木常忍の導きで文応元年頃に入信し門下になったといわれている。曾谷入道も同じ頃に大田左衛門尉とともに入信したと伝えられている。3人とも学識があり裕福でしばしば大聖人に御供養していたという。3人は親しい間柄で富木常忍と共に下総の信徒の中心的な存在だったようである。
《御書のポイント》
◆法華経という正法を行じるからこそ、過去世の謗法によって未来に重苦を受けるところを今世において軽く受けて消すことが出来る。
◆悪世末法に仏の教え通りに修行することは難しいこと。そして、その末法に法華経を身で読んでるのは大聖人ただお一人であるということです。
御書講義
8月度座談会御書履歴
座談会御書 「減劫御書」2000年(平成12年)
座談会御書 「阿仏房御書(宝塔御書)」2001年(平成13年)
座談会御書 「四条金吾殿御返事(世雄御書)」2002年(平成14年)
座談会御書 「高橋殿御返事(米穀御書)」2003年(平成15年)
座談会御書 「四条金吾殿御返事」2004年(平成16年)
座談会御書 「一生成仏抄」2005年(平成17年)
座談会御書 「上野殿後家尼御返事(地獄即寂光御書)」2006年(平成18年)
座談会御書 「四条金吾殿御返事(世雄御書)」2007年(平成19年)
座談会御書 「減劫御書」2008年(平成20年)
座談会御書 「窪尼御前御返事」2009年(平成21年)
座談会御書 「四条金吾殿御返事(源遠流長御書) 」2010年(平成22年)
座談会御書 「持妙法華問答抄」2011年(平成23年)
座談会御書 「聖人御難事」2012年(平成24年)
座談会御書 「千日尼御前御返事」2013年(平成25年)
座談会御書 「曾谷殿御返事」2014年(平成26年)
座談会御書 「四条金吾殿御返事(八風抄)」2015年(平成27年)
座談会御書 「千日尼御前御返事(雷門鼓御書)」2016年(平成28年)
座談会御書 「阿仏房御書(宝塔御書)」2017年(平成29年)
座談会御書 「松野殿御家尼御返事」2018年(平成30年)
座談会御書 「崇峻天皇御書(三種財宝御書)」2019年(平成31年)
座談会御書 「転重軽受法門」2020年(令和02年)
座談会御書 「減劫御書」2021年(令和03年)
座談会御書 「妙密上人御消息」2022年(令和04年)
座談会御書 「四条金吾殿御返事(衆生所遊楽御書)」2023年(令和05年)
座談会御書 「四条金吾殿御返事(八風抄)」2024年(令和06年)
8月の広布史 ★8月24日★
――「池田先生 入信記念日」――
昭和22年8月24日
■小説「人間革命」2巻 第5章「地涌」
■今日より明日へ №17
「8・24」記念大田・世田谷・杉並区合同支部長会(東京)
〝本物の一人〟よ出でよ
■今日より明日へ №38
「8・24」記念―第1回東京総会
――「聖教新聞創刊原点の日」――
昭和25年8月24日
■小説「人間革命」4巻「怒清」
1950年(同25年)、戸田第2代会長(当時・理事長)の事業が苦境に陥る中、聖教新聞発刊の構想を、戸田会長と若きSGI会長が語り合った日が淵源。
――「壮年部の日」――
昭和51年8月24日
■黄金柱の誉(創価学会壮年部指導集)
1976年(昭和51年)6月、副会長室会議で定められた。