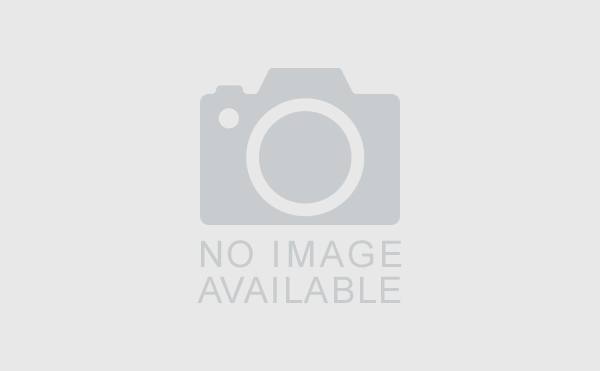座談会御書 日眼女造立釈迦仏供養事2025年(令和7年)6月度
〈御 書〉
御書新版 1610㌻4行目~5行目
御書全集 1187㌻6行目~8行目
御書講義の流れ
最初に、基礎教学の復習をします。「一つ目は御本尊について」「2つ目は仏法僧の三宝について」「3つ目は御本仏について」になります。
続いて、本文・通解・背景そして私の考察となります。また、今回の御金言を通して、池田先生の御指導を紹介します。
終わりに、身延の教義と同じ「釈迦本仏論」へと変更しようと、「創価学会教学要綱」を発行した第六天の魔王と化した執行部の破折をし、いかに自活グループが創価の希望であるかを紹介します。
〈基礎教学の復習〉
1、御本尊について
まず初めに、基礎教学の「御本尊」です。
本来の創価学会の御本尊の定義として、三大秘法の大御本尊及び人法一箇の大御本尊が挙げられます。
三大秘法とは本門の本尊、本門の戒壇、本門の題目を指します。本門とはSokanet教学用語検索からは、「法華経28品の後半の14品ではなく、大聖人の文底の法門」を意味します。
また人法一箇とは、人・法の名称は異なっても、その体は同じ。「人」とは、人の本尊たる御本仏日蓮大聖人であり、「法」とは、法の本尊たる事の一念三千、南無妙法蓮華経の御本尊を意味します。
2、仏法僧の三宝について
次に「仏法僧の三宝」です。
本来の創価学会の仏法僧の三宝の定義は、仏宝は日蓮大聖人、法宝は三大秘法の御本尊、僧宝は日興上人を指します。
自活ホームページにある「やっぱりおかしい『創価学会教学要綱』シリーズ」に掲載されていますが、学会は三代会長以来、法華本門を表として、その文底にある「日蓮大聖人に備わる南無妙法蓮華経」こそ真実の「法」であるとして、人法一箇・三大秘法の法宝としてきました。また僧宝について、これまで学会は大聖人の仏法を正しく受け継いだ人として「日興上人」としてきました。
3、御本仏について
最後に「御本仏」についてになります。
御本仏に関しては、正法・像法の時代の御本仏は釈尊になります。しかし、今日末法の時代の御本仏は日蓮大聖人になります。
更に説明いたします。
釈尊の仏法は「久遠実成」になります。この釈尊の仏法、就中、法華経本門の教えとして、釈尊は『法華経如来寿量品』で「我は実に成仏して以来、無量無辺の劫を経た」と宣言し、従来の「始成正覚(35歳で初めて悟った)」の立場を超え、久遠の過去(五百塵点劫)から仏であったことを明かしました。時間軸で見ると「五百塵点劫」という有限です。これが「久遠実成」の教義です。
また釈尊の仏法は「本果妙」と呼ばれ、悟りの結果(果)としての仏を説きます。釈尊は「成仏した仏」として衆生を導きますが、成仏の原因(因)を明かさないという限界がありました。
それに対して、日蓮大聖人の仏法は「久遠元初」になります。この大聖人の仏法は、法華経文底の法門として、釈尊の久遠実成を更に遡り、無始無終の法の根源「久遠元初」を顕しています。これは「五百塵点劫の当初」を超え、時間を離れた宇宙生命の根本法(南無妙法蓮華経)を指します。
また大聖人の仏法は、釈迦の仏法の「本果妙」に対して、「本因妙」と呼ばれています。成仏の根本原因(因)である妙法を直ちに説きます。衆生が凡夫のまま題目を唱えて成仏できる道を開き、「因行果得」の二法を一瞬で獲得する法になります。
撰時抄冒頭には「夫れ仏法を学せん法は必ず先づ時をならうべし。」とあるように、「時」を学ぶ必要があります。今は末法です。
末法の御本仏は「日蓮大聖人」であり、法華経も文底秘沈、宇宙生命の根本である南無妙法蓮華経になります。大聖人の仏法は「本因妙」になります。
ーまとめー
先に説明した、御本尊・三宝・御本仏を通して、戸田第二代会長、池田第三代会長の御指導を御紹介したいと思います。
戸田先生の御指導
「久遠実成の釈迦如来は、我本行菩薩道において、南無妙法蓮華経を修行したことは歴然としています。ただ化導にあたっては、釈尊は南無妙法蓮華経とはいわないのです。法華経28品を言ったにすぎないのです。南無妙法蓮華経は、その釈尊の所有物ではありません」(戸田城聖全集第6巻P.474)
また、「人法一箇とは、仏法の大眼目であり、正邪の判別はこれにある。南無妙法蓮華経即日蓮大聖人であるにもかかわらず、邪宗では、南無妙法蓮華経の法を立て、久遠実成の釈迦を人に立てている。人法のそろわぬことは大問題である」(『戸田城聖全集』第4巻P.67)
池田先生のご指導
「妙法は大宇宙の根源の法である。その法を久遠元初以来、悟り、所持されているのが日蓮大聖人であられる。人法一箇の妙法であり、御本尊も「南無妙法蓮華経 日蓮」とお認めである」(『池田大作全集』第84巻、永遠に自在の境涯を開こう、P.198)
〈本 文〉
譬えば、頭をふればかみゆるぐ。心はたらけば身うごく。大風吹けば草木しずかならず。大地うごけば大海さわがし。教主釈尊をうごかし奉れば、ゆるがぬ草木やあるべき、さわがぬ水やあるべき。
〈通 解〉
たとえば、頭を振れば、髪が揺れる。心が働けば、身体が動く。大風が吹けば、草木が揺れる。大地が動けば、大海も荒れる。教主釈尊を動かせば、揺るがない草木があるだろうか。騒がない水があるだろうか。
〈背 景〉
本抄は、日蓮大聖人が身延の地から、鎌倉に住む四条金吾の妻・日眼女に送られた手紙です。最新の研究では、弘安3年(1280年)、59歳の御時の御述作とされています。この年、日眼女は38歳の厄年にあたっていました。当時の人々は、厄年は厄災に遭う恐れのある年、節目の年として、様々な備えをしていました。その中で日眼女は厄年に際し、大聖人に真心の御供養を行ったのです。その日眼女に対して、厄年の用心といっても、その根本は、日蓮大聖人が顕された大本尊に対してどこまでも深い信心と、どんなものをも突き動かす強き一念の祈りに立つことであると励まされています。
〈考 察〉
日眼女が弘安3年の段階においても釈迦の仏像を作ったのは、僧侶の弟子に対するのとは違って、武家の、それも御婦人レベルでは、深い法門の教示がなされていなかったか、あるいは、なされていたとしても、理解できなかったためだと推測します。夫の四条金吾ですら、よく分かっていなかったのではと推測できます。
下総(今の千葉県北部)の大田金吾や曾谷入道も、迹門不読の僻見を抱いて、大聖人から「無間大城に落ちるぞ」と厳しく叱責されるような状況でしたから、教学を教育することがいかに大変だったことがうかがわれます。
鎌倉時代とは違って教育環境が整っている今日においてすら、教学に関心がなかったり、無頓着なメンバが多い学会です。教学がわからなくても、池田先生を慕っているメンバーみたいなものかもしれません。副会長・方面長クラスですら、教学がない人はゴロゴロといます。
大聖人は、念仏等の邪宗があふれかえっていた当時において、法華経と釈尊を大切にした日眼女を漸進主義の観点から抱擁しつつ、丁寧に法門を御指南されていったと想像します。
この御書で大聖人は、「教主釈尊」との言葉を使われていますが、同時に釈尊や法華経を『太陽』ではなく『月』に譬ています。
この御書を著された同年に、門下一同の為に著されたとみられる「諌暁八幡抄」では、「天竺国をば月氏国と申す、仏の出現し給ふべき名なり。扶桑国をば日本国と申す、あに聖人出で給はざらむ。月は西より東に向へり。月氏の仏法、東へ流るべき相なり。日は東より出づ。日本の仏法、月氏へかへるべき瑞相なり。月は光、あきらかならず。在世は但八年なり。日は光明、月に勝れり。五五百歳の長き闇を照らすべき瑞相なり。仏は法華経謗法の者を治し給はず、在世には無きゆへに。末法には一乗の強敵充満すべし、不軽菩薩の利益此なり。各々我が弟子等はげませ給へ、はげませ給へ」(P.1543)と記されており、月と太陽を挙げて、釈尊・釈迦仏法より、大聖人・日蓮仏法が優れていると示されています。
御金言を通しての池田先生の御指導紹介します。
「頭をふればゆるぐ」―頭をふれば、当然、髪の毛は揺れる。「心はたらけば身うごく」とは、私達は、こうしたい、ああしたいという願望、または、こうしなくてはいけない、こうしようといった義務感、決意等々、心の働きをもとに行動することは当然であります。 「大風吹けば草木しずかならず」―大風が吹けば、草木は当然大きく揺れていく。「大地うごけば」とは地震であります。「大海さはがし」―地震が起これば、当然、波が高まり、津波とか高波が起こってくる。ちょうどこのように「教主釈尊をうごかし奉れば」―ここで、教主釈尊とは、末法今時においては、日蓮大聖人のことであり、すなわち大御本尊のことであります。したがって「教主釈尊をうごかす」とは、私どもの信力そして行力によって、仏力・法力を湧現していくことである。仏力法力とは大御本尊のお力であります。(東北本部幹部会 日眼女 1968.3.25 「池田大作講演集」第1巻)
大風吹けば草木しずかならず、大地うごけば大海さはがし。教主釈尊をうごかし奉れば、ゆるがぬ草木やあるべき、さわがぬ水やあるべき、について-日眼女の供養した釈迦像を賛嘆するためにこのような表現をとられているが、「教主釈噂」とは、大聖人の御内意においては人法一箇の御本尊のことである。自身においては根本の生命、仏界の生命である。(日蓮大聖人御書講義第24巻 P.300)と御指導されています。
〈自活グループが創価の希望〉
創価学会執行部により「釈迦本仏論」への教義変更がなされ、身延化する実態について、説明させて頂きます。
実際に池田先生が2010年に第一線を退かれてから、2015年4月、2019年4月に、今回の御金言の全く同じの御金言を座談会御書として2回ほど、掲載されています。
その中の背景と大意でも、2回とも「教主釈尊=仏=南無妙法蓮華経」となっております。詳細に関しては、URL先を御参照下さい。
また、創価学会公式Youtubeにおいて、今月の御書講義を教学部副書記長が担当され講義されています。その中で、深瀬教学部副書記長は愚かにも「教主釈尊は南無妙法蓮華経と一体である」と、身延教学を口にしました。これには本当に驚きました。
またSokanetの教学用語検索ページでは、いつのまにか、三大秘法の根幹である「人法一箇」を教学部は削除し、創価学会ホームページの教学用語集にはもはや「人本尊」や「法本尊」の記載もありません。釈迦をどうしても本仏にしたいようです。
創価学会公式動画で、しかも教学部の副書記長が身延教学を堂々と講義していることについては、もはや学会執行部としての正式見解としてみるしか他ならないと、強く危機感を感じています。
釈尊は南無妙法蓮華経を覚知していたのかも知れませんが、時未だ至らぬため、南無妙法蓮華経を法華経に文底秘沈し、末法に出現する久遠元初自受用身如来に託します。また大聖人は立正安国論をはじめ、様々な御書の中で末法においては釈尊の説いた法華経も力はなく、ただ南無妙法蓮華経のみを信じるべきであると説かれています。
これらで明らかなように、「教主釈尊とは御本尊である」とか「教主釈尊と南無妙法蓮華経は一体である」とするのは、人法一箇とは矛盾します。
教主釈尊こそが久遠元初の本仏で、日蓮大聖人は上首上行菩薩であるとするのは、「釈迦本仏論」を唱え大聖人を釈迦の下に位置付けた身延教学と同じ、日蓮仏法を曲解する邪義であると断言できます。
御本尊の御相貌を見れば明らかです。中央に大きく「南無妙法蓮華経 日蓮」と書かれ、釈尊はその脇士として上部に「南無釈迦牟尼佛」と書かれています。
これが大聖人のご内証を現された御本尊が教主釈尊と一体ではないことの厳然たる証拠です。
また創価学会発行の「創価学会教学要綱」には仏法僧の三宝を、「仏宝=日蓮大聖人 法宝=南無妙法蓮華経 僧宝=創価学会」と変更しました。
一見してわかるように、法宝は御本尊から題目にかわり、僧宝は日興上人から創価学会に変わっています。日蓮大聖人については最後まで末法弘通の使命を釈尊から託された「釈迦仏の使い」「上行菩薩の再誕」としています。「本因妙抄」「百六箇抄」「御義口伝」など日興門流の相伝書を一切無視し、相伝書を重視された日寛上人の御指南に違背しています。この態度は、「教学は日寛上人の時代に帰れ」と指導され、日寛教学を基本とされた戸田第二代会長を初めとする三代会長の指導にも違背するものです。
続いて、「創価学会教学要綱」から見る現執行部が第六天の魔王である証明と、その執行部と戦う自活グループのメンバーの希望と明るい将来を示し続ける実証を讃嘆したいと思います。
まずは現執行部が第六天の魔王である証明です。
今回の御書講義を始め、大白蓮華にある背景と大意は、明確に「創価学会教学要綱」に沿ったものです。
「創価学会教学要綱」は学会の名のもと、発行しています。しかもその「教学要綱」は、『池田先生監修』と先生を利用するだけならまだしも(それも許される行為ではないですが…)、もはや三代会長をも愚弄していると言わざる得ません。
「教学要綱」は、あまり現時点では会員に対しては浸透はせず、今はなりを潜めている形になっていますが、近い将来いずれ学会執行部は、先生の名のもとこの愚書「教学要綱」を学会のドクトリン(教学の中枢)とすること間違いないことが明白となりました。いや、既に着実に実行に移されています。
自活グループはそういう魔に対して厳然と堂々と戦いを開始しています。
魔は見えないところから、着実に中枢まで進行しています。第六天が恐ろしいのは明白ですが、本当に見分けにくいとは先生がよくおっしゃっておられていました。先生は「敵は内部だよ!」とはこのことかと、気づかされました。
まさに今が学会の転換期です。ここで魔と戦って人生を勝利で飾るか、あるいは魔と気づかず、あるいは魔とわかっていても戦わず、我関せずと師敵対でいるのか。
私は愚弟・末弟ではあれど、池田先生の弟子として、学会中枢に巣くう魔と戦う決意はできています。
実際、三障四魔が憤然と競い起こってきていることを実感しています。これこそ弟子の誉だと確信しています。
まがいなりとも、先生の弟子と名乗り、少しでも師恩に報いるのであれば、今がその時だと声を大にして言いたい。先生が手塩にかけて育ててきた学会を、学会精神を決して忘れてはいけない。弟子であると自覚するならば、今の執行部と戦わなければならないと感じています。
第六天の魔王はもはや宗門ではなく、間違いなく学会執行部です!
魔と戦う「自活グループ」のメンバーは必ず大聖人・三代会長から讃嘆され、功徳溢れる将来が約束されていること間違いなし!
共々に頑張りましょう!
-願いが叶う祈り方-
最後に本御金言のまとめとして、「願いが叶う祈り方」を説明して終わりにします。
私自身の経験になりますが、企業に属している以上、成績が上がらなければ当然首は免れません。成績は、当然自分の力で勝ち取る必要があるのですが、時には自分の力ではどうしても解決できない、例えば企業の政治的力、社会状況、景気動向等によって自分ではどうしても何ともできない状況もあったりします。
私自身、何度もこの苦境を、まさにこの御金言の通り、怒涛のお題目と決意、行動で乗り越えてきました。
「お題目をあげているけれど願いが叶わない」、「お題目をあげたけれど何も変わらない」こういう声を、よく耳にします。
けれど、それは祈り方が間違っているからです。
今回拝する『日眼女造立釈迦仏供養事』は、まさに「願いが叶う祈り方」を教えてくださっている御書です。
私たちが御本尊に祈るのは、いわゆる「おすがり信心」ではありません。 御本尊に「何とかしてください」と願うだけでは、なかなか叶いません。
この信心は、自分自身の一念によって祈りを叶える信心です。つまり、祈りとは「頼む」ことではなく、自分自身が「決める」ことなのです。「絶対に何とかしてみせる」、「必ず叶えてみせる」、「絶対に勝つ!」――このように決意することが、すなわち祈るということなのです。
自分の一念が定まるからこそ、御本尊の「力用」が現れるのです。 御本尊は自分の生命を映す鏡です。 中央にしたためられた「南無妙法蓮華経 日蓮」は、私達の仏界そのものの生命を顕したものであり、その仏界の一念に応じて、周囲の仏・菩薩・諸天善神が呼応し、働き出してくれます。 この働きの先頭にいるのが「南無妙法蓮華経」の左側に書かれている教主釈尊すなわち「南無釈迦牟尼佛」です。
これが今回の御文にある――「教主釈尊をうごかし奉れば」――という意味なのです。 御本尊に向かい「教主釈尊よ、動きたまえ」と、釈尊を動かすような強い一念で祈る。 頭を振れば髪の毛が揺らぐように、心が動けば、身体もそれに従って動く。大風が吹けば、草木は必ず揺れる。 大地が揺れれば、大海もまた荒れる。
それと同じように、教主釈尊を動かす一念で祈れば、その祈りに呼応しない天地はありません。
「弥三郎殿御返事」(御書全集1451頁)には、こうあります。
「釈迦・多宝・十方の仏、来集して我が身に入りかはり我を助け給へと観念せさせ給うべし」この御指南も、「仏を動かす一念の祈り」を表しています。
戸田先生は、次のように指導されています。
「釣鐘を、楊枝でたたくのと、箸でたたくのと、撞木(しゅもく)でつくのとでは、音が違うだろう。 同じ釣鐘だが、強く打てば強く響き、弱く打てば弱く響く。 御本尊も同じだ。こちらの信力・行力の強弱によって、功徳に違いがあるのだよ」
「信力」とは、御本尊を信じぬく力。 「行力」とは、題目を唱え、人のため、社会のために広宣流布に励む力です。 「仏力」とは、仏が衆生を救わんとする誓願の力。「法力」とは、妙法そのものが持つ、絶大な生命変革の力です。つまり、こちらの信力・行力が強ければ強いほど、仏力・法力が力強く呼応して現れるのです。
ですから、「絶対に、祈りが叶わないわけがない」――との大確信をもって、御本尊に向かい、題目を唱えていくことです。 そして何よりも、仏法を弘める「広宣流布」の実践に生きる時、 自身の内なる仏界の生命が躍動し、人生に功徳としてあらわれてきます。 決める。祈る。叶える。これが日蓮仏法のあり方です。
御書講義 動画サイト
6月度座談会創価の森御書履歴
座談会御書 「辨殿尼御前御返事」2000年(平成12年)
座談会御書 「四条金吾殿御返事(法華経兵法事)」2001年(平成13年)
座談会御書 「四条金吾殿御返事(梵音声御書)」2002年(平成14年)
座談会御書 「法華初心成仏抄」2003年(平成15年)
座談会御書 「呵責謗法滅罪抄」2004年(平成16年)
座談会御書 「四条金吾殿御返事(法華経兵法事)」2005年(平成17年)
座談会御書 「富木尼御前御返事(弓箭御書)」2006年(平成18年)
座談会御書 「辨殿尼御前御書」2007年(平成19年)
座談会御書 「立正安国論」2008年(平成20年)
座談会御書 「四条金吾殿御返事(法華経兵法事)」2009年(平成21年)
座談会御書 「上野殿御返事(竜門御書)」2010年(平成22年)
座談会御書 「法華経題目抄」2011年(平成23年)
座談会御書 「祈祷抄」2012年(平成24年)
座談会御書 「四条金吾殿御返事(法華経兵法事)」2013年(平成25年)
座談会御書 「妙心尼御前御返事」2014年(平成26年)
座談会御書 「四条金吾殿御返事(不可惜所領事)」2015年(平成27年)
座談会御書 「祈祷抄」2016年(平成28年)
座談会御書 「四条金吾殿御返事(法華経兵法事)」2017年(平成29年)
座談会御書 「単衣抄」2018年(平成30年)
座談会御書 「呵責謗法滅罪抄」2019年(平成31年)
座談会御書 「曾谷殿御返事」2020年(令和02年)
座談会御書 「祈祷抄」2021年(令和03年)
座談会御書「四条金吾殿御返事」2022年(令和04年)
座談会御書 「上野殿御返事(水火二信抄)」2023年(令和05年)
座談会御書 「曾谷殿御返事(成仏用心抄)」2024年(令和06年)
6月の広布史
――初代会長牧口先生 誕生日――
6月6日
■小説・人間革命
第1巻 黎明
■小説 新人間革命
第18巻 師子吼・師恩
■小説 新人間革命
第25巻
■池田大作全集
牧口先生生誕記念協議会2005年6月6日
■広布と人生を語る
初代会長牧口常三郎先生誕生日」記念勤行会1986年6月6日
――学生部結成記念日――
6月30日
■小説・人間革命
第11巻 波瀾・夕張
■小説 新人間革命
第28巻 広宣譜