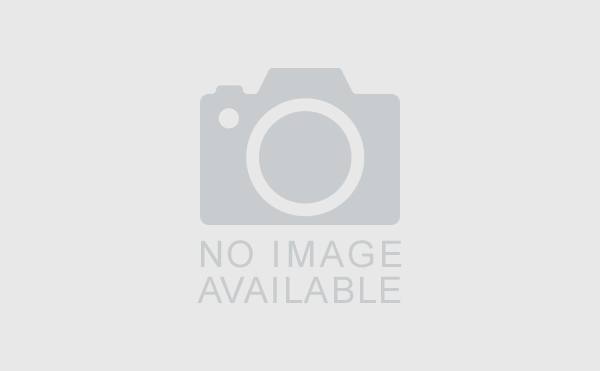座談会御書「単衣抄」2025年(令和7年)5月度
〈御 書〉
御書新版 1849㌻4行目~6行目
御書全集 1514㌻13行目~15行目
〈本 文〉
日蓮、日本国に出現せずば、如来の金言も虚しくなり、多宝の証明もなにかせん、十方の諸仏の御語も妄語となりなん、仏の滅後二千二百二十余年、月氏・漢土・日本に「一切世間多怨難信」の人なし、日蓮なくば仏語既に絶えなん。
〈通 解〉
日蓮が日本国に出現しなかったならば、釈尊の金言も虚言となり、多宝如来の証明も何の役にも立ちません。十方の諸仏の御語も妄語となっていたでしょう。
仏の滅後二千二百二十余年の間、インド・中国・日本に「一切世間に怨嫉が多くて信じ難い」の経文を身で読んだ人はいません。日蓮が出現しなかったならば、仏の語もすべて絶えてしまったでしょう。
〈講 義〉
本抄は建治元年(1275年)8月、日蓮大聖人が54歳の時に身延で著されました。
本抄の題号は後世につけられたものと思われます。
誰に与えられたお手紙かは諸説あり不明ですが、御文の中で「未だ見参にも入らぬ人」と仰せられていることから、まだ一度も大聖人が会われていない信徒からの真心の御供養に対して心を込めて与えられたお手紙と思われます。
本抄全体の内容としては、始めに単衣と呼ばれる、裏地のついていない着物で夏前後に着る衣服の御供養を受けられたことを述べ、法華経を身読して仏語を実語とした大聖人への御供養は、そのまま法華経への功徳となり、その功徳によって成仏は間違いないと仰せられています。
全体を大きく三段で分けると、
一段目で、単衣の御供養を受けられたことを述べられたあと、法華経のゆえに日蓮大聖人ほど国中のあらゆる人から憎まれた人はいないことを述べられ、寺を追われ、住処を追われ、親族を苦しめられ、夜討ちなどにもあい、傷を負わされたり、弟子を殺されたり、頸の座にもすえられ、二度の流罪にも処せられて法華経を身読したことを述べられています。立宗以来あらゆる迫害にあいながら片時も身心の休まる暇が無かったと仰られています。
次に、二段目で、法華経法師品の「如来の現在にすら猶怨嫉多し」と法華経安楽行品の「一切世間怨多くして信じ難し」を引かれ、天台・伝教もこの経文を身で読むことは無かったと述べられたあと、今回拝読する部分の日蓮大聖人が法華経を身読されて釈尊の言葉を実語にして、多宝・十方の諸仏の証明を真実とした。もし日蓮大聖人が出現しなかったら釈尊の説法も多宝・十方の証明も嘘となり、仏法も途絶えていたと述べられています
そして最後の三段目で
身延での生活がいかに大変かを述べられた後、そうした時に、まだ会ったこともない信徒からの真心の単衣を御供養されたことを称賛し、一つの単衣でも法華経の行者である日蓮大聖人が身に着け、法華経を読まれるならば、法華経の文字六万九千三百八十四字の一つ一つの仏に単衣を供養したのと同じであり、その諸仏の加護によって、現世は安穏であり、臨終の時も必ず護られると約束され、その功徳の大きさを示されています
この単衣を供養した信徒は、どれほど歓喜したことかと思います。
ここで全体を貫く大切なポイントとして
●日蓮大聖人の身(人の御本尊)が即法華経(法の御本尊)という「人法一箇」を前提に考えなければ正しく本抄を読み取ることができないと言えます。
・日蓮大聖人が過去に誰もあったことのない迫害・大難にあわれ法華経を身読したこと
・日蓮大聖人がなければ釈尊の法華経や多宝・十方の諸仏の証明も嘘となったこと
・一つの単衣でも法華経の行者である日蓮大聖人が身に着け法華経を読まれるならば法華経の文字六万九千三百八十四字の一つ一つの金色の仏に単衣を供養したのと同じであるということです
「人法一箇」を前提に考えなければ正しく本抄を読み取ることができないと言いましたが、どこぞの宗教団体は釈尊も大聖人も「根本の法である南無妙法蓮華経によって仏になった」と言っているようですが、大昔から法のみが存在して、仏が無かった時代があったと言っているようなもので、最早、三世常住の仏ではありませんし、これでは時間軸を横長にしてのみでしか見ていないことになります。
また、法のみであれば「理」であり仏界といっても「あるかもしれない」という可能性の域を出ません。「理」はどこまで行っても「理」です。
この単衣抄はある意味で、日蓮大聖人は南無妙法蓮華経如来であると宣言をしている書であると読み取れます。
「事」は実体があって初めて「事」であるのであって日蓮大聖人は即法華経(御本尊)であり南無妙法蓮華経は即仏身です。
池田先生も「法華経の智慧」4巻80ページで、『「法」といっても「人(仏)」と離れた法は「理」だけの存在です』と御指導頂いています。
また、これは私たちの御本尊様への向き合い方や関係を示す上で、最も重要なことと思います。
南無妙法蓮華経が仏身の当体である御本尊・日蓮大聖人を「一大秘法」として、その「本門の本尊」を開いた時に、御本尊に唱える題目を「本門の題目」として仏の力用を示し住する場所(国土)を「本門の戒壇」とするのであって三大秘法といってもそれぞれが別々に存在するものではありません。
そして、日蓮大聖人であり仏を生む側の能生の御本尊を境として、我々が題目を唱えるから境智冥合し、生み出される側の私たちの所生の御本尊が開かれるのです。
だからこそ御本尊(日蓮大聖人)を大切に受持し、御本尊に題目を唱え、御本尊に御供養をすることで、我々の色心も取巻く環境である国土も変わっていくのだと思います。
これを簡潔に言うと「祈りが叶う」となるのではないでしょうか。
三大秘法の大御本尊です。三大秘法と言っても「本門の本尊」「本門の題目」「本門の戒壇」はそれぞれ別のものを示すのではなく、御本仏日蓮大聖人御一身のことです。
そして、今回の御文を拝する時、三代会長、なかんずく池田先生の創価学会が無ければ御本仏日蓮大聖人の法門は証明されなかったと言えます。
同様に私たち自活の友はそれを踏まえ、御本尊(日蓮大聖人)を大切にし、御本尊(日蓮大聖人)にお題目を唱え、供養し、この身に、自身の環境に、池田先生の弟子らしく法華経の行者として現世安穏・後生善処の実証を示していくことで、池田先生の指導が正しかったと証明していくことが一番大事であると確信します。
生きていれば大変なことは沢山ありますし、悩みは絶えません。
しかし、その苦難をもすべて成功の実証を示す上で大切なプロセスとして、今日から更に人生のすべてを楽しむ出発の日としていきたいと思います。
御書講義 動画サイト
御書研鑽しよう会創価の森
5月度座談会御書履歴
座談会御書 「寂日房御書」2000年(平成12年)
座談会御書 「異体同心事」2001年(平成13年)
座談会御書 「上野殿御返事」2002年(平成14年)
座談会御書 「十字御書」2003年(平成15年)
座談会御書 「さじき女房御返事」2004年(平成16年)
座談会御書 「異体同心事」2005年(平成17年)
座談会御書 「阿仏房御書(宝塔御書)」2006年(平成18年)
座談会御書 「千日尼御前御返事」2007年(平成19年)
座談会御書 「千日尼御前御返事」2008年(平成20年)
座談会御書 「四条金吾殿御返事(不可惜所領事)」2009年(平成21年)
座談会御書 「種種御振舞御書」2010年(平成22年)
座談会御書 「四条金吾殿御返事(煩悩即菩提御書)」2011年(平成23年)
座談会御書 「開目抄」2012年(平成24年)
座談会御書 「椎地四郎殿御書」2013年(平成25年)
座談会御書 「呵責謗法滅罪抄」2014年(平成26年)
座談会御書 「富木尼御前御返事(弓箭御書)」2015年(平成27年)
座談会御書 「開目抄」2016年(平成28年)
座談会御書 「四条金吾殿御返事(法華経兵法事)」2017年(平成29年)
座談会御書 「椎地四郎殿御書」2018年(平成30年)
座談会御書 「種種御振舞御書」2019年(平成31年)
座談会御書 「開目抄」2020年(令和02年)
座談会御書 「立正安国論」2021年(令和03年)
座談会御書 「開目抄」2022年(令和04年)
座談会御書「顕仏未来記」2023年(令和05年)
座談会御書「妙密上人御消息」2024年(令和06年)
5月の広布史
――創価学会の日――
5月3日
■随筆 平和の城
晴れ渡る五月三日
■人間と仏法を語る11巻(今日より明日へ31巻)
5・3「創価学会の日」記念勤行会
――創価学会母の日――
1988年(昭和63年5月3日)
■人間と仏法を語る7巻(今日より明日へ10巻)
4・27 第1回全国婦人部幹部会
■人間と仏法を語る7巻(今日より明日へ11巻)
5・3 「創価学会の日」記念式典
■池田SGI会長指導集 「幸福の花束」―平和を創る女性の世紀へ
婦人部の歩み