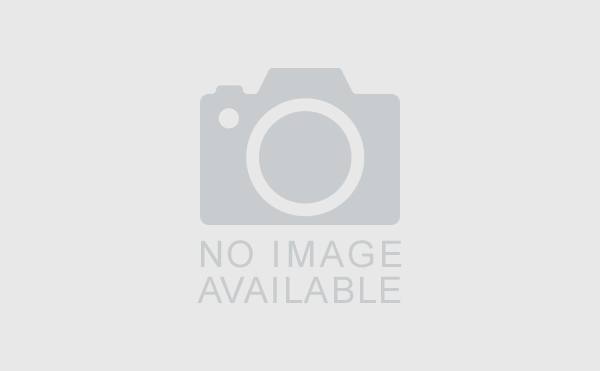安房国清澄寺に関する一考 35

ここでは頼瑜(嘉禄2年・1226~嘉元2年・1304)の弟子・頼縁と法鑁(日吽)、寂澄らの事跡を確認し、清澄寺での真言・東密の法脈の可能性を探ってみましょう。
【 寂澄 】
寂澄の手択本(しゅたくぼん・持ち主が手元に置いて愛読した本)は称名寺に多数残されており、どのようなものを伝領・書写・伝持したのか、「金沢文庫古文書」に収録された奥書を確認することで寂澄の法脈が理解できます。
◇「不動法」
文永七年(1270)庚午二月廿二日 亥時書写了 寂澄 春秋□二十九
(識語編2・P299 No2146)
◇「不動法」
文永七年(1270)八月十九日 寂澄 春秋□二十九
(識語編2・P299 No2147)
◇「胎蔵界自受法楽説」
文永七年(1270)庚午十一月十二日 寂澄
(識語編2・P144 No1584)
◇「自性法身能加持説」
文永七年(1270)庚午十一月十三日 寂澄
(識語編1・P286 No961)
この写本により、寂澄は頼瑜教学を学んでいたことが窺われます(櫛田・続P231)。
その場所については、櫛田氏は金沢・称名寺としているようですが、その典拠はあるのでしょうか。寂澄の手択本が称名寺に伝来しているといっても、その学習場所までは特定できないと考えます。
◇「金剛界自受法楽説」
文永七年(1270)庚午十一月廿日 寂澄
(識語編1・P225 No760)
◇「二界他受用法身説法」
文永七年(1270)庚午十一月廿一日 寂澄
(識語編2・P215 No1854)
これら寂澄による文永7年(1270)の書写本、11月12日「胎蔵界自受法楽記」、11月20日「金剛界自受法楽説」、11月21日「二界他受用法身説法」により、寂澄の周辺では頼瑜の「加持身説」が談議されていたことが確認されます(櫛田・続P231)。
◇「四種曼荼羅義」
建治元年(1275)乙亥七月十七日 右幹寂澄
(識語編1・P283 No949)
◇「三部細行口伝幷加行次第表白」
弘安五(1282)六九日 寂澄 花押
(識語編1・P260 No881)
◇「最極秘密羅誡記」
弘安五(1282)六九日 寂澄 花押
(識語編1・P243 No821)
◇「覚源深理論」
永仁六年(1298)戊戍五月十一日 右翰寂澄
(識語編1・P62 No219)
◇「聞持秘事」
正安元年(1299)己亥八月十二日 右翰寂澄 春秋□五十八
清澄山
(識語編3・P63 No2425)
◇「蝕時露地法」
正安元年(1299)己亥八月十三日 右翰寂澄 五十八
(識語編2・P68 No1283)
◇「虚空蔵菩薩念誦法」
正安(1299)己亥八月十七日 右翰寂澄 五十八
清澄山
(識語編1・P200 No660)
◇「摩界得脱啓白」
正安二年(1300) 庚子十二月十三日 金剛仏子良―云々 釈寂澄
(識語編3・P37 No2316)
◇「神供幷破壇等」
正安二(1300) 庚子十二廿一 寂澄
(識語編2・P83 No1336)
◇「八千枚等文集」
正安□十二月廿六日校点了 寂澄
(識語編2・P250 No1971)
◇「求門持 私」
已上表裏所載者、抄集儀軌幷大師御説、又衍師蓮
師予見等明哲所伝、尤納笞底莫他散而已
高祖十五代資 寂澄
正安三年(1301)辛丑正月三日
(識語編1・P123 No437)
◇「両部曼荼羅秘要決」
正安三年(1301)辛丑正月九日 以右本書写了
金剛資寂澄
(識語編3・P119 No2576)
◇「続曼荼義」
正安三年(1301)辛丑正月十五日 書写了
金剛末資寂澄
(識語編2・P118 No1469)
◇「法身偈」
正安三年(1301)辛丑正月廿七日 以右本書写了
金剛資寂澄
(識語編3・P8 No2218)
◇「梵字」
(朱)正応三年(1290)四月十四日於鎌倉
佐々目御房奉伝受了
右朱点口伝也。加私之。 金剛資心
正安三年(1301)辛丑二月二日 於清澄寺書写了
金剛資寂
(識語編1・P251 No845)
◇「梵字」
正安三年(1301)辛丑五月廿七日 金剛資寂澄
正安三年(1301)辛丑六月十六日 於清澄寺書写了
金剛資寂澄
(識語編2・P99 No1396)
◇「梵字」
正安三年(1301)辛丑六月廿三日書写畢
金剛資寂澄
正安三年(1301)辛丑十月書写了
金剛資寂澄
(識語編2・P294 No2122)
◇「梵字」
正安四年壬寅三月廿一日
金剛資 寂澄
(識語編2・P186 No1742)
◇「虚空蔵一印口決」
正安四六廿日書写了 右翰金剛資寂澄
(識語編1・P199 No655)
◇「阿闍梨寂澄自筆納経札」
房州 清澄山
奉納
六十六部如法経内一部
右、当山者、慈覚開山之勝地
聞持感応之霊場也、仍任
上人素意六十六部内一部
奉納如件、
弘安三年(1280)五月晦日 院主阿闍梨寂澄
(早稲田大学所蔵文書)
文永7年(1270)の「不動法」はどこで書写したのか明らかではありませんが、弘安3年(1280)5月の「院主阿闍梨寂澄自筆納経札」と併せ考えると、鎌倉等で修学していた時期を除き、弘安3年(1280)の「院主」であった時から正安3年(1301)の20年以上、寂澄は清澄寺に居住したことになります。また、文永7年(1270)から正安4年(1302)にかけて書写、相伝したものに頼瑜と覚鑁のものが少なからずあり、寂澄は東密・新義真言の法脈に連なる人物であったことが確認されるのです。