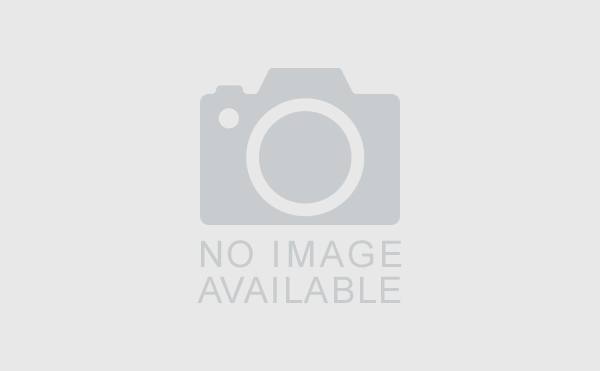座談会御書「法華初心成仏抄」2025年(令和7年)10月度
〈御 書〉
御書新版697㌻14行目~16行目
御書全集552㌻14行目~16行目
〈本 文〉
とてもかくても法華経を強いて説き聞かすべし。信ぜん人は仏になるべし。謗ぜん者は毒鼓の縁となつて仏になるべきなり。何にとしても仏の種は法華経より外になきなり。
〈講 義〉
本抄は大聖人の御真筆が現存しておらず、ご執筆時期や対告衆については詳しいことはわかっておりません。学会版御書では、本抄のご執筆を建治三年としておりますが、その他にも文永期や弘安期など諸説あり、いずれも現時点では年代を特定する明確な根拠は見いだせておりません。対告衆につきましては、本文中に女人成仏について言及され、「南無妙法蓮華経と唱え奉る女人は、在世の竜女・憍(きょう)曇(どん)弥(み)・耶輸陀(やしゅた)羅女(らにょ)のごとくに、やすやすと仏になるべし」などと述べられていることから、女性門下に与えられたものと考えられ、一説には駿河在住の女性門下に宛てられたものともされておりますが、この点につきましても人物を特定する十分な根拠が見いだせていないため詳細は不明です。
本抄全体の概要ですが、本抄は13 の問答形式で構成されており、冒頭、「数ある宗派の中で、釈迦仏の立てた最も正しい宗派は何であるか」との設問に対し、「法華宗は釈迦の立てたもうところの宗なり。その故は、『已説・今説・当説の中には法華経第一なり』と説き給う。」と答えられ、法華経こそが最上第一の教えであり仏の真意であることが説かれます。続いて、法華経が随一の教えであることの根拠について、教の高低浅深を示し、法華経以前の釈尊一代の諸経は、衆生のさまざまな機根に合わせて説かれた教えであり、次第に機根を整えて一切衆生を法華一乗に帰すことを目的とした方便であって、万人成仏を説く法華経こそが真実の教えであることを教えられています。
続いて、「大集(だいしっ)経(きょう)には、末法は釈尊の説いた一切の経説が力を失う『白法隠没』の時であることが説かれているため、最上第一の法華経でさえも末法ではその功力を失ってしまうのではないか」との問いを立てられ、その答えとして「末法では法華経の肝心である南無妙法蓮華経が上行菩薩によって弘められ、一切衆生を利益するのである」とされ、よき師とよき法とよき檀那との三つが寄り合い、一致した時に初めて真の利益を発揮し、国土が安穏になるとの法理を明かされています。そして、末法は濁悪の世であり、衆生はすべて無智・邪智であるから、妙法を強いて説き聞かせ毒鼓の縁を結んでいくことが肝要であると述べられ、勧持品の経文を通し、末法の逆縁の衆生に法華経を弘める行者には必ず三類の強敵が競い起ることを教えられています。
最後に、三世諸仏も妙法蓮華経の五字によって仏になったのであるから、そのことをよくよく心得て一途に南無妙法蓮華経と唱えていくことこそが、末法における真実の成仏の道であることを述べられて本抄を結ばれています。
それでは、今月の拝読箇所に移ります。御書全集は552 頁14 行目、新版御書は697 頁14行目となります。
「とてもかくても法華経を強いて説き聞かすべし。信ぜん人は仏になるべし。謗ぜん者は毒鼓の縁となって仏になるべきなり。いかにとしても、仏の種は法華経より外になきなり。」
通解です。
「とにもかくにも、法華経寿量文底の南無妙法蓮華経を強いて説き聞かせていきなさい。即座に信じる人は仏となり、たとえ誹謗する者も毒鼓の縁となりこの妙法によって必ず成仏するのである。仏になるための仏種とは南無妙法蓮華経以外には無いのである。」
末法において正法を弘めるにあたっての心構えと「聞法下種」の重要性を教えられています。これまで何度も拝してきた御文ですが、あらためて今の私たちにとってピッタリの大切な教えではないかと思います。
末法は、正法への不信謗法が渦巻く社会であるため、妙法を弘めようとするならば必ず摩擦や反発が起こります。この御文では、相手が信じようと信じまいと、悪口誹謗しようとも、いかなる謗法の人であっても必ず仏縁を結ぶことができ、この妙法によって救っていけるのだから、むしろ反発する人にこそ強いて法を説き聞かせ、成仏の道を開いていくべきであるとの御本仏の揺るぎない大確信と、一切衆生を救済せずにはおられないとの大慈悲のご境涯が拝されます。
創価三代の会長、なかんずく池田先生は、この御金言のままに全人類救済の大願に立ち、広布の途上において巻き起こる幾多の摩擦や抵抗を真っ向から受け止め、乗り越えて、今日の偉大なる世界広布の礎を築いてこられました。草創の先達の方々も、折伏に歩けば悪口を言われ、塩をまかれながら、それでも自他共の幸福を願い、この人も救いたい、あの人にも幸せになってほしいとの思いで仏法を語りぬいていきました。どんなにバカにされ、いじめられても、「徹して一人を大切に」との精神で、不撓不屈の戦いを重ねてきたがゆえに、学会は大発展し、世界中に人間同士の信頼と共感の輪を広げることができたのです。
ところが、2010年、池田先生がお倒れになり、表舞台に出られなくなった直後より、原田執行部らによる学会乗っ取り計画の策謀が動き出しました。根幹となる教義をねじ曲げ、永遠に留めるべき師匠の歴史、思想、指導などを改ざん、破棄し、三代会長が創られた学会から崇高な師弟の精神が失われていきました。人よりも組織が優先され、会員を隷属させるために組織を権威化させて組織絶対化を図り、学会の変節を憂う心ある会員の声には耳も傾けず、「反逆者」のレッテルを張り付けて切り捨てました。三代の会長や草創の先達の方々が命がけで築いてきた一大和合僧団は、権威主義、組織主義の団体へと変貌し、同時に大聖人の仏法を唯一正しく受け継いできた教団としての正統性も失われてしまいました。
このような無慈悲、残酷、非道の原田学会がいかに大聖人や池田先生を敬っているように見せかけ、御本尊を拝み、「われ創価学会仏なり」などと息巻いたところで、格好だけで、その内実は大聖人と師匠の心に違背しているがのですから、功徳どころかかえって大罰を受けることになります。また、どんなに会員をあおって数を増やすことができたとしても、それは誤った教えが広まるだけで、ただただ人々や社会に害毒をまき散らすことにしかなりません。
原田学会の出現によって、大聖人の正統を継ぐ教団が消滅してしまった今、広宣流布の運動は従来の組織型の活動形態から、自立した一人ひとりが自ら考え、行動する自発能動の信仰実践によって広布を切り開いていく、個人主体の活動形態へとシフトしてきたと思います。この意味においても、自立した信仰者が異体同心して広布へ向かう私たち自活の果たすべき使命はいやまして大きいと感じざるをえません。
さて、この「法華初心成仏抄」には、私たちが祈りを成就させ、国土を安穏にし、広布を実現しゆくためには、「よき師」と「よき法」と「よき檀那」の三つが一致しなければならないとの重要な法理が示されています。これは、妙法の真の功徳を受けるための必須条件であるとともに、私たちが常に正しい信心に立ち返るための重要な指針であると思いますので、御文を通して共に学んでいきたいと思います。
はじめに大聖人は、「現世安穏・後生善処なるべきこの大白法を信じて国土に弘め給わば、万国にその身を仰がれ、後代に賢人の名を留め給うべし。知らず、また無辺行菩薩の化身にてやましますらん。また、妙法の五字を弘め給わん智者をば、いかに賤しくとも、上行菩薩の化身か、また釈迦如来の御使いかと思うべし。」と述べられ、末法には妙法を説き明かす上行菩薩の化身たる智者と、妙法を護持し国土に弘める無辺行菩薩の化身たる在家の賢人が出現することが説かれています。
続いて、「末法今の世の番衆は上行・無辺行等にておわしますなり。これらを能く能く明らめ信じてこそ、法の験(しるし)も仏菩薩の利生も有るべしとは見えたれ。(中略)よき師と、よき檀那と、よき法と、この三つ寄り合って祈りを成就し、国土の大難をも払うべきものなり。」とされ、上行菩薩の化身たる「よき師」と、無辺行菩薩の化身たる「よき檀那」がそれぞれ誰なのかということをよくよく明らかにした上で、「よき師」と「よき法」と「よき檀那」の三つが寄り合って初めて祈りも成就し国土も安穏にできる、とご断言されています。
「よき師」とは、垂迹上行菩薩の再誕、本地久遠元初の自受用身たる末法の御本仏日蓮大聖人、「よき法」は三大秘法の妙法、すなわち御本尊のことになりますので、問題は、「よき檀那」がいったい誰なのかということになります。大聖人は「よき檀那」の人物像について、「現実の上で国土に妙法を弘め、万国にその存在を讃えられ、後々まで賢人として名を残す人」であるとされています。これはあくまでも私見ですが、この御文にあてはまる在家の賢人とは池田先生をおいて他にはおられないと思います。
事実、池田先生という偉大な在家賢人の出現によって、御文のとおりに妙法が国土に広まり、未曽有の世界的な仏法興隆が実現し、大聖人のご予言を実現させたことこそが何よりの証明ではないでしょうか。
よって、現在においては御本仏日蓮大聖人、御本尊、そして師匠池田先生に直結することが最も正しい信心の姿勢であり、祈りを成就させ、広布を実現するための必須条件ということになります。そして、その師弟直結の信心こそが、「よき師」と「よき法」と「よき檀那」が一致した姿に通じ、私たちの生命に大聖人の正統の血脈を流れ通わせ、妙法の偉大な力用を発揮させゆく勝利の要諦となるのです。「直結」とは、文字通り双方の間に雑物を入れず、直接結びつけるとの意ですので、御本仏、御本尊、師匠と私たちの間には、いかなる媒介物も存在しないし、また存在させてはならないということです。私は、師弟直結の信心とは、どこまでも師匠を求め抜き、師匠の振舞いや精神を根本としていく生き方のことではないかと思います。
その意味においても、毎月の自活座談会や、オンラインスタディーを通し、師弟直結の正しい信心、正しい教学を学び、広布にまい進する私たち自活の実践こそ、まさに時に適った信仰の在り方であり、心ある会員にとっての希望の灯台であると確信します。現在、私のまわりでも続々と自活の同志が誕生し、晴れ晴れと先生直結の信心を開始しており、その方々のすがすがしい信心の姿、歓喜の姿、勝利の姿を目の当たりにするたびに、私自身もいやまして自活信仰の正しさを実感しています。これからも、その自負と確信をもって、堂々と前進を続けてまいりたいと思います。
それに引き換え、保身のために先生や仏法を利用し、会員を組織に直結させ、師匠と会員を分断した原田学会がどれほど悪逆非道であるか。かつて先生が「組織はあくまで、この(御本尊と自分)直結をより深くするという根本目的のための手段と言っても過言ではないでしょう。この目的と手段をはきちがえる時、その組織はたちまち権威主義とドグマに囚われ、民衆を苦しめる魔物と転化するのであります。」(百六箇抄講義)と教えてくださいましたが、まさに現在の原田学会の姿そのものであり、原田学会こそ「よき師」「よき法」「よき檀那」の全てに背き、社会を不幸にする現代の一凶です。
また、池田先生は、「仏法上の狂いは、多くの人々を迷わせ、成仏の道を閉ざすことになる。だからこそ、悪を放置してはならない。戦わねばならない。戦うことが、仏法の正義を守ることになり、民衆を守ることになる。」(1991.8.18 第四回北海道総会、県・区代表幹部会)と御指導されています。この御指導通り、今や狂った原田執行部による仏法破壊の暴挙によって多くの会員が惑わされ、成仏の道を閉ざされてしまいました。
ゆえに、原田学会の悪を責め、今なお悪しき組織信仰から抜け出せずにいる一人でも多くの学会員を救っていくこともまた、大聖人、創価三代会長の正統を継ぐ私たちの重要な使命であると思います。
私も、組織で共に戦ってきた大切な仲間が、一日も早く極悪原田学会の実態に気づき、正しい信心の軌道に乗れるようにと、相手の心田に新たに仏種を植え付けるような思いで祈り、対話に挑戦しています。
当然、話を聞いてすぐに共感を示し、決然と立ち上がる方ばかりではありません。話はうなずいて聞いてくれるものの結局はどこか他人事のようにしか受け止めてもらえなかったり、時には血相を変えて反発され、無認識な批判、悪口にさらされることもあります。
同じく随力弘通に励む皆さんも、「どうしてわかってもらえないのだろう」と、歯がゆい思いをすることが多々あるかと思います。そんな時こそ、「とてもかくても法華経を強いて説き聞かすべし。信ぜん人は仏になるべし。謗ぜん者は毒鼓の縁となって仏になるべきなり。いかにとしても、仏の種は法華経より外になきなり。」との大聖人の御断言を胸に刻み、堂々と戦い抜いていきたいと思います。
これからも共々に、池田先生直結の門下としての誇りを胸に、互いに励まし、讃えあって、元気に楽しく前進していきましょう。
以上です。ありがとうございました。
御書講義 動画サイトほか
10月度座談会御書履歴
座談会御書 「三三蔵祈雨事」2000年(平成12年)
座談会御書 「四条金吾殿御返事(八風抄)」2001年(平成13年)
座談会御書 「曾谷殿御返事(成仏用心抄)」2002年(平成14年)
座談会御書 「聖人御難事」2003年(平成15年)
座談会御書 「寂日房御書」2004年(平成16年)
座談会御書 「椎地四郎殿御書」2005年(平成17年)
座談会御書 「兵衛志殿御返事」2006年(平成18年)
座談会御書 「持妙法華問答抄」2007年(平成19年)
座談会御書 「乙御前御消息(身軽法重抄)」2008年(平成20年)
座談会御書 「諸法実相抄」2009年(平成21年)
座談会御書 「兄弟抄」2010年(平成22年)
座談会御書 「上野殿後家尼御返事(地獄即寂光御書)」2011年(平成23年)
座談会御書 「佐渡御書」2012年(平成24年)
座談会御書 「寂日房御書」2013年(平成25年)
座談会御書 「日女御前御返事(御本尊相貌抄)」2014年(平成26年)
座談会御書 「妙密上人御消息」2015年(平成27年)
座談会御書 「聖人御難事」2016年(平成28年)
座談会御書 「四条金吾殿御返事(八風抄)」2017年(平成29年)
座談会御書 「日女御前御返事(御本尊相貌抄)」2018年(平成30年)
座談会御書 「可延定業書」2019年(平成31年)
座談会御書 「一生成仏抄」2020年(令和02年)
座談会御書 「千日尼御前御返事(真実報恩経事)」2021年(令和03年)
座談会御書 「佐渡御書」2022年(令和04年)
座談会御書「報恩抄」2023年(令和5年)
座談会御書 「聖人御難事」2024年(令和6年)
10月の広布史
――「世界平和の日」――
昭和35年10月2日
■池田大作全集 第126巻 随筆 129㌻
■大道を歩む 私の人生記録