日蓮大聖人と 法華経の関係について (教学の基礎として)

投稿者:伊東 浩
今回は教学の基礎として「日蓮大聖人と法華経の関係」について解説していきたいと思います。
もちろん、たかだか数枚の原稿で語り尽くせるとは思っていませんが、その概略だけでも伝えることができれば嬉しく思います。
それではまず、その関係についてはじめに「教学要綱」を確認します。要綱では顕仏未来記の「三国四師」(新版612㌻)の御文を挙げて次のように解説しています。
「天台大師・伝教大師らの思想を継承し、『法華経』を釈尊のすべての教えの肝要であると捉え、『法華経』の身読を貫かれたのが、日蓮大聖人である。(中抜) 釈尊(インド)、天台大師(中国)、伝教大師(日本)、そして日蓮大聖人(日本)を『三国四師』と呼び、この四人を大乗仏教の真髄である『法華経』を弘通する系譜として位置づけられたものである。大聖人は、『法華経』の肝心である『南無妙法蓮華経』が人々を救済する根本法であると覚知し、『南無妙法蓮華経』を三大秘法として具体的に示して、万人成仏を実現する方途を確立された」(要綱36㌻) ※下線筆者
と。
この説明が合ってるのか間違っているのかよく分からないという人もいますが、この説明にはただ「法華経」と明記しているだけで、そこには「本迹・理事」の勝劣も「種脱」の区別もなく、押並べて「法華経」と表現しているに過ぎません。
これを額面通りに解説すれば、日蓮大聖人は三師(釈尊・天台・伝教)の思想を継承し、法華経身読を貫かれた。その三師に自身を加えて大乗仏教の真髄たる「法華経」(経典)を弘通する系譜の人と位置づけられた。そして法華経(文上脱益)の肝心たる妙法蓮華経に帰命する「南無妙法蓮華経」が人々を救済する根本法であると覚知し、それを三大秘法として具体化した——となります。
教学を長年学んできた人なら「非常に雑多で中途半端な説明である」と感じているのではないかと思います。なぜこんな説明になるのかというと、恐らく「教学要綱刊行委員会」の人たちは、法華経は釈尊の説いた「二十八品」のみと思っているからではないかと思います。そしてその根っこにあるのは、終始一貫して「法華経」を中心に大聖人の弘教を判断していることです。
法華経には、正法時代の法華経、像法時代の法華経、末法時代の法華経と三種の法華経があります。正法は釈尊の説いた「二十八品」であり、像法は天台の説いた「摩訶止観」(一念三千論)であり、末法は大聖人の説いた文底下種・久遠名字の「南無妙法蓮華経」と三大秘法です。大聖人の教義を中心にして「教学要綱」の解説を読めば、釈尊の法華経(妙法蓮華経)を中心に三大秘法を具体化したことになり、どこをどう読んでも文底下種・久遠名字の「南無妙法蓮華経」を中心に三大秘法を具体化したことにはなりません。
そもそも大聖人と法華経の関係は、日蓮教学を正しく理解するうえでもっとも重要な問題です。古来、日蓮門下は「法華経」を中心に大聖人の弘教を判断していこうとするものと「大聖人」を中心に法華経を判断していこうとするものとに分かれ、、その二つの立場が基礎となって日蓮門流は様々な分派に分かれていった歴史があります。
そこでまず日蓮教学を学ぶ大前提として、「法華経中心」に大聖人の弘教を判断するのか、それとも「御書中心」に判断するかの立場をはっきりとさせた上で、「大聖人と法華経の関係」を、順を追って解説していきたいと思います。
【御書中心か、法華経中心か】
先ほども言いましたが、大聖人の教義を学ぶうえでもっとも重要な問題の一つは、この「大聖人と法華経」はどのような関係にあるのかを正しく理解していくことにあります。というのは、ある意味でこの問題が大聖人の教義そのものと言っても過言ではないからです。大聖人滅後、日興上人(富士派)をはじめとする五老僧(身延派)はこの立場が違っていたがゆえに大きく二つに分かれていきました。これが「五一の相対」です。
日興上人は大聖人が書き残された「御書」を中心にして法華経を判断していきましたが、五老僧は終始一貫して「法華経」を中心に大聖人の弘教を判断していきました。
たとえば、大聖人の「法華経最第一」とする権実二教の戦(振舞い)を見て、大聖人が諸宗を破折されたのは「法華経」そのものを弘通すめためであるとするものや、自ら「天台沙門」と名乗り、宗祖はあくまでも天台の法華経解釈の研鑽を積み重ねた「法華経の行者」であり、天台とは別の解釈をもって「法華経」を弘通したのであるという弟子もいました。
それに対して、日興上人は「御書」を通して日蓮教学が何であるかを明快に示し、それらの邪義を論破していきました。
ではなぜこのような見解の違いに分かれたのかというと、大聖人の最初の弟子はそのほとんどが仏教学として天台教学を学び、そのあとに大聖人の教義を学んでいました。そのためどうしても彼らは天台教学から抜け出すことが出来ず、大聖人の立てる教義を真に理解できた者はいなかったのです。
これについて日興上人は『遺誡置文』の中で、
「日蓮仏法の教義と道理をしっかり胸に収めて習得することが先であり、そこまで至らない中途半端なままで天台教学を学んではならない」(十条)、また「(大聖人の)御書を心肝に染め、その極理を師から受け伝えて、その上でもし〝いとま〟があれば、天台教学を学ぶべきである」(十一条)と厳命しています。
これは日蓮仏法を学ぶ者は、まずその態度、立場をはっきりと決定して教義を学ぶべきであると教えられたものですが、同時に天台教学を中心に日蓮教学を学ぶという風潮にあった当時の弟子に対する戒めのご指導でもありました。
この厳格な日興上人の姿勢を手本として、大聖人の教義はあくまでも「御書」によって決定することが最も正しいあり方です。
教学要綱では、三国の師(釈尊・天台・伝教)に大聖人を加えてこの四人を「法華経を弘通する系譜として位置つげられた」(要綱)としていますが、厳密に言えば間違いです。
大聖人は三国(釈尊・天台・伝教)の法華経の「師」(行者)を受け継いで、末法に南無妙法蓮華経を弘通してきたと述べられ、自身を加えて「三国四師」と名づけると宣言されていますから、これは「法華経を弘通する系譜」ではなく、法華経の精神を受け継いだ真正の「法華経の行者の系譜」であると受け止めるのが御書を中心とした正しい解釈であると考えます。
【弘教の順序】
大聖人はあらゆる角度からご自身が弘通する法門を説いていますが、大聖人の最後に行き尽く化導は何かといえば、三大秘法(事の一念三千)の法門を立てそれをもって衆生を成仏させることにあります。すなわち大聖人の教義は、「三大秘法」が如何なる法門であるかということに尽きています。これが日蓮教学の根本です。
御書を中心にして大聖人の弘教をたどっていくと、そこには大きく分けて三つの段階があることが分かります。まず大聖人の弘教の第一は、最勝第一の法華経を押し立てることにありました。その理由は、大聖人ご在世当時の仏教界は天台伝教によって法華経が「最勝第一」と論証されたにも関わらず、その法華経が第二第三と下され「権実雑乱」の様相を呈していたからです。
大聖人が「法華経」を下す諸宗の謗法を破折されたのは、法華経そのものを弘通するためではなく、法華経の権威を現してこそ初めて末法に「上行菩薩」と「三大秘法」が出現する理由が明らかになるからです。弘教の第二は、末法時代の法華経たる本法(三大秘法)を建立して、一切衆生に授けこれを受持させていくことを目的としたことです。そして弘教の第三は、その三大秘法が法華経の所説(教相)とどのような関係にあるのかを明示したことです。
大聖人は「法門のことは、さどの国へながされ候いし已前の法門は、ただ仏の爾前の経とおぼしめせ」(新版2013㌻)と仰せられていることからも大聖人の弘教に段階があったことが推察でき、特に佐渡期の前と後において重大な転換があったことが伺えます。
【大聖人の正統性】
では、「法華経」は誰のために説かれたかというと、一つは釈尊在世の衆生のため、もう一つは釈尊滅後の衆生のためです。大聖人は「滅後(正像末)の中でも末法をもって正意とし、末法の中でも日蓮をもって正意とする」(法華取要抄)と仰せです。
これは、滅後末法に登場する日蓮のために法華経は説かれたのだという意味ですが、その根拠とされたのは、もちろん「法華経」です。
法華経では明確に「末法」の時が示され、末法における「法華経の行者」のために法華経が説かれたことが明かされています。(安楽行品第十四) そして悪世末法の法華経の弘通者に「三類の強敵」による迫害があることが明かされており(勧持品第十三)、その予言は大聖人の受難の様相と一致します。したがって、法華経迹門が「末法」のために説かれ、大聖人(法華経の行者)を正意とすることは明白です。
次に法華経本門には上行菩薩が「三大秘法」を建立することが説かれています(寿量品第十六)。「三大秘法」は寿量品の文底に秘沈されている仏種(南無妙法蓮華経)を顕したもので、この三大秘法を釈尊は「四句の要法」として上行菩薩に付属しました(神力品第二十一)。
大聖人は、「寿量品の自我偈に云わく『一心欲見仏 不自惜身命(一心に仏を見たてまつらんと欲して、自ら身命を惜しまず)』云々。日蓮が己心の仏界を、この文に依って顕すなり。その故は、寿量品の事の一念三千の三大秘法を成就せること、この経文なり」(義浄房御書)、また「問うて云わく、如来の滅後二千余年、竜樹・天親・天台・伝教の残したまえるところの秘法は何物ぞや。答えて曰わく、本門の本尊と戒壇と題目の五字となり」(法華取要抄)と仰せです。
この「法華経本門」と「御書」の御文によって明らかな通り、寿量品の極説は「三大秘法の南無妙法蓮華経」であり、その妙法は釈尊によって上行菩薩にすべて手渡されたのです。したがって、末法万年における妙法の所在は釈尊にあるのではなく、上行日蓮その人(ご本仏)にあることは明らかです。
だからこそ大聖人は「されば無作の三身とは末法の法華経の行者なり。無作の三身の宝号を南無妙法蓮華経と云うなり。寿量品の事の三大事とはこれなり」(御義口伝)と仰せなのです。
【まとめ】
それでは最後にまとめていきたいと思います。
日蓮大聖人と法華経の関係は、冒頭で確認した「教学要綱」のような単純でいいかげんな理屈ではなく、第1に法華経が「上行菩薩の出現」と上行菩薩が建立する「三大秘法」が明示されていること。第2に大聖人はそれに呼応して出現し「三大秘法」を建立したこと。第3に「三大秘法」は大聖人の我見の法門ではなく、法華経から外れることなく、法華経の教相(所説)に立って明示していったこと。——この3つが「大聖人と法華経の関係」の骨子であり結論です。
大聖人の「権実二教の戦」(諸宗謗法の破折)は、法華経そのものの弘教ではなく、法華経の権威を取り戻し、末法に「上行菩薩」と「三大秘法」が出現する理由(因縁)を明らかにするためです。大聖人の法華経身読は「上行再誕」の予言を証明し、それと同時に釈尊の所説(法華経)は虚妄でないことが証明されました。
またそれは「三大秘法の南無妙法蓮華経」の正統性を確保するためでもあります。
冒頭で解説した「三種の法華経」(釈尊・天台・日蓮)に共通するものは、
〝万人が等しく成仏の可能性をもっている〟という教えに尽きています。これが時代を超越した「不変の真理」です。それを釈尊は「二十八品」の法華経で表現し、大聖人は法華経の極理を「三大秘法の南無妙法蓮華経」として示されました。
万人成仏の法を説けば、必ず大難に遭います。釈尊も「九横の大難」に遭いました。しかも末法にこの法華経を弘めれば、必ず釈尊以上の大難が競うことが説かれています。
大聖人は経文通り寸分も違わず大難に遭われた姿(法華経身読)をもって、我(日蓮)こそが末法の「法華経の行者」であることを宣言し、それとともに天台・伝教もそれぞれの時代の「法華経の行者」として位置づけています。これが「三国四師」(法華経の行者の系譜)の真意です。
大聖人は決して法華経の教相(所説)から外れることなく、天台の法華経解釈(三大部)を用いて、寿量品から「文底」を導き出し、法華経を「文上脱益」(迹門)と「文底下種」(本門)に区別しました。この「種脱相対」(種本脱迹)が大聖人の教義です。
彼らはこの「種脱相対」(種本脱迹)を理解していない、もしくは知らないからこそ、
「大聖人は『法華経』の肝心である『南無妙法蓮華経』が人々を救済する根本法であると覚知し『南無妙法蓮華経』を三大秘法として具体的に示して」(要綱)などと、恥ずかしげもなく無知丸出しで書けるのです。これが現学会の教学レベルの実態です。
以上で終わります。
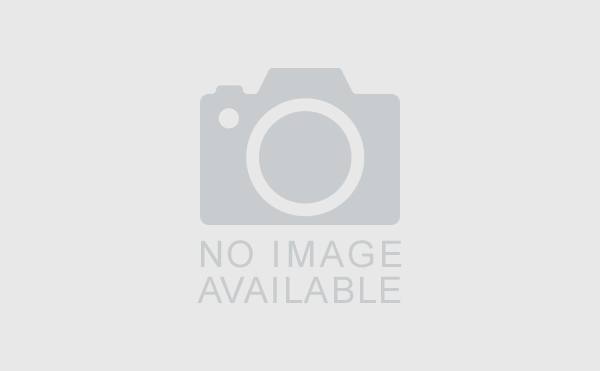
法華経と言っても印度応誕の釈迦が直接説いたものでなく何百年も経ってから、サンスクリット語で創作的に纏められ、更に漢訳されたものです
したがって釈迦が南無妙法蓮華経(この語自体が漢訳法華経を前提にしている)によって成仏したということ自体が完全なフィクションに思われます
日蓮大聖人は南無妙法蓮華経を広め、法華経に説かれる難を受けることによって、法華経に説かれる内容が、単なる想像の世界ではなく、現実にあり得ることを証明されました
このことによって、法華経に説かれる釈迦の久遠(五百塵点劫)の成道も真理である事が推察できることになると考えます
南無妙法蓮華経という表現は漢訳法華経の経題をベースにしているものの日蓮大聖人の創作と言えるから、釈迦を久遠(五百)の仏に成し得たのは、まさしく日蓮大聖人の実践によるといえると思います
またこのことから、法華経は日蓮大聖人の御出現の予証になっているものと考えます
なお、法華経が十界互具を説いて万人成仏を説くと言っても、万人が仏であるとする如来蔵思想には至っていません
日蓮大聖人は諸法実相抄で「凡夫は体の三身にして本仏ぞかし、仏は用の三身にして迹仏なり、然れば釈迦仏は我れ等衆生のためには主師親の三徳を備へ給うと思ひしに、さにては候はず返つて仏に三徳をかふらせ奉るは凡夫なり」として、如来蔵思想を読み込んでいます
この御文の「凡夫」こそ日蓮大聖人であり、釈迦を久遠(五百)の仏になさしめたのは日蓮大聖人その人と読むべきと考えます
したがって、日蓮大聖人は法華経が予言した末法の救世主であるとともに、釈迦をも成仏(久遠五百)させた根源仏であると捉えるべきと考えます