【投書】【指導の学び直し】日蓮大聖人・身延離山の決断と、いま私たちが受け継ぐべき信仰の魂

投書者:虹さん
【引用元:参考指導】
聖教新聞2008年8月7日3面(池田大作全集未収録)
青年部代表研修会での名誉会長のスピーチ③
「世間にへつらい正義を曲げた」
一、日蓮大聖人が入滅された後、高弟であった六老僧のうち、日興上人以外の五老僧は皆、大聖人の教えに違背した。
日興上人は、五老僧の一人で、身延離山の原因をつくった日向の本性について、次のように喝破されている。
「世間的欲望が強くて、世間にへつらい、正義を曲げた僧で、大聖人の御法門を世に立てることなど思いもよらず、大いに破る者である」(編年体御書1732ページ、通解)
世間からほめられたい。認められたい。そうした名聞名利を求める心のゆえに、五老僧は、大聖人の正法正義をねじ曲げてしまったのである。
これまでの学会の反逆者の多くも、同様であった。
また日興上人は、「『師を捨ててはいけない』という法門を立てながら、たちまちに本師(大聖人)を捨て奉ることは、およそ世間の人々の非難に対しても、言い逃れのしようがないと思われる」(同1729ページ、通解)と述べ、師に違背した者たちを厳しく指弾しておられる。
仏法の「師弟の道」は厳しい。しかし、真実の師弟に生き抜く人生は幸福である。皆様は、創価の「師弟の道」を、まっすぐに歩み抜いていただきたい。
「富士一跡門徒存知(ふじいっせきもんとぞんち)の事」には、「日蓮大聖人の例にちなみ、日興が6人の弟子を定めた」「この6人は和合して、異議があってはならないことを協議し、決定した」(御書1603ページ、通解)と記されている。
〈日興上人は大聖入滅後16年目の永仁(えいにん)6年(1298年)に6人の高弟(本六)を定められた。さらに入滅前年の元弘(げんこう)2年(1332年)に新たに6人の高弟(新六)を定められた)
広宣流布のために、弟子が一致団結できるかどうか。師匠の教えのままに、生き抜けるかどうか。
ここに未来の一切がかかっているのである。
引用終わり
=============================
◇「身延離山の決断と、いま私たちが受け継ぐべき信仰の魂」
日蓮大聖人がご入滅された後、その教えを継ぐはずだった高弟たち。
――六老僧のうち、日興上人を除く五老僧は、大聖人の正法(指導)を守りきれませんでした。
日興上人はその姿を見て、こう喝破されています。
>「世間的欲望が強くて、世間にへつらい、正義を曲げた僧で、大聖人の御法門を世に立てることなど思いもよらず、大いに破る者である」
(編年体御書1732ページ、通解)
五老僧は、世間的な評価や名聞名利の誘惑に屈してしまったのです。そして権力への迎合が、仏法の根幹である正法をねじ曲げる結果を招いた。
この歴史は、遠い昔の話ではありません。現代においても、まったく同じ構造が創価学会で繰り返されているように感じます。
池田先生が命をかけて築かれた創価学会。その精神を受け継ぐべき幹部たちの中に、権力への迎合があれば、それはまさしく五老僧と同じ過ちではないでしょうか。
池田先生が命を削るように伝えてくださった、正しい信仰が、原田会長と執行部の手により形骸化の危機に瀕しているように見えます。
◇「身延離山」の目的と今
日興上人が身延を離山されたのは、師匠・日蓮大聖人の仏法を守るためでした。弟子として、いかに愛着があろうとも、正法を曲げてまで妥協することはできなかった。それが、離山の決断だったのではないかと感じます。
それは、今日における「魂の独立」に通じます。
誰かに依存する信仰ではなく、自分で思索し、自分で選び取る信仰。
自立であり自活です。
自立した信仰者には、「師の心」に生き抜こうとする深い覚悟が奥底に芽生えてきます。
池田先生は、日蓮大聖人と日興上人の「師弟の魂」を、現代に甦らせて遺されたのです。
私は、池田先生の弟子として生きているか?
組織の空気や幹部の顔色に流されていないか?
生きた宗教を体現しているか?
池田先生の指導を学び直すとき、時を超え日蓮大聖人の一念が我が身に熱く蘇ります。
歴史は繰り返される。
しかし、私は繰り返さない
五老僧の逸脱も、創価の歴史における幾多の反逆者たちも、その根は同じです。
「権力への迎合」で、師恩を濁してしまった。いや、踏みにじった!
信仰とは自己責任であり、世間の基準では計れない尊き選択の連続です。
日興上人は、こう言われました。
>「『師を捨ててはならぬ』という法門を立てながら、たちまち本師を捨てた者は、世間の人々にも言い訳ができない」(御書1729ページ、通解)
私たちが本当に大事にすべきなのは、「誰の弟子であるか」という一点ではないでしょうか。
そしてそれは、「形式」ではなく「心」です、一念です。
自己責任で決めることです。
どこまでも池田先生の誓願に生きようとしているかどうか。
師弟不二であり続けることが、信仰の根幹と私は決めています。
希望はどこにあるか――私たち一人ひとりの命にある。
命には無限の可能性があると学びました。
創価学会が、再び「池田先生の魂」によって甦る鍵は、一人の弟子の人間革命にあります。
組織がどうか、――それらを問う前に、自身が「池田先生の弟子として、今を、どう生きるか」を模索し決断することです。
歴史を変えるのは、常に一人の「無名の庶民」からです。
そして、そこには必ず池田先生への「師恩」が息づいていると信じています。
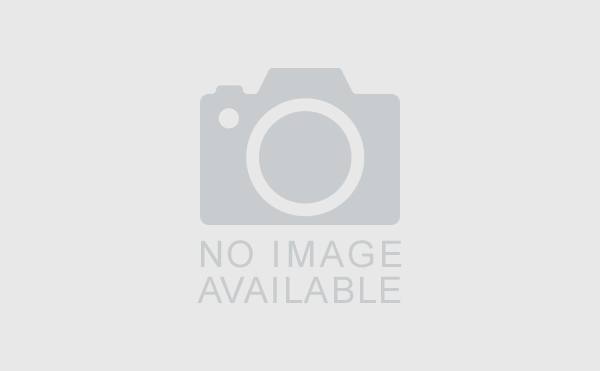
虹さん様
ご投稿に深く賛同いたします。私も五老僧の如く生き方は絶対にしないですし、そのような人生には陥らない事を誓って生きていきます。
師弟不二の人生を歩む事は厳しき道ですよね!あるいは池田先生のご期待通りの行動は出来ていないかもしれませんが、幼少の頃から池田先生の弟子であるとの意識を忘れた事はありません。
今後も池田門下生であるとの心根を抱きながら生きていきます!
素敵なご投稿をありがとうございました!
仰せの通りと同意致します。「先生!」「先生!」と言っていた多くの学会員が、かくも簡単に師弟の道を踏み外す。何と悲しい現実でしょうか。
騙す方が悪いのは元よりですが、騙される会員、または騙されている事にも気付けない多くの学会員が、不憫でなりません。
「あなた達は、一体何を学んできたのか?」
真の信仰を貫くのは、とても難しいということでしょうか・・。