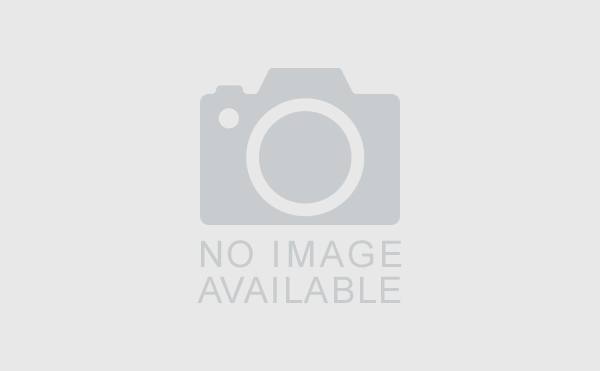依正不二について (教学の基礎パートⅳ)

投稿者:伊東浩
前回のオンスタでは、生命の本質を追究した「色心不二」ついて解説しましたが、今回はその色心不二なる生命と私たちを取り巻く環境や国土の関係を究明した「依正不二」について解説していきたいと思います。
前回のオンスタでも話しましたが、人間は昔から唯物論者と唯心論者が対立しそれが自由主義や共産主義と変化してその主義のもとに破壊的な戦争をしてきました。これをさらに広げて見ていくと、同じように「人間」と「環境」の関係に対する見方の違いにも現れ、いわゆる人間の意識が根本か、環境が根本かという対立が見て取れます。
たとえば「唯物論側」に立つものは自然や環境が〝意識を決定する〟と信じて人間を環境の一分だと考える見方と「唯心論側」に立つものは人間の意識は環境の如何に関わらず〝独立している〟という見方の違いがあります。つまり、生命の本質を究明した色心不二に対して、依正不二は〝生命の場〟である環境と意識の関係(本質)をどう見るかという対立です。
色心不二をはじめとする生命 (主体)と環境(客体)の関係を明確にしていない「生命論」(哲学)は、たとえそれがどのように理論付けられようとも、それは単なる抽象論にすぎません。なぜかといえば、あらゆる生命はその生命が存在するための環境があり、その環境や国土を抜きにして生命の存在を明らかにしたことにはならないからです。
たとえば、地球に空気がなければ私たちはたった一時間でも生き続けることはできないし、太陽がなければ生物は皆死に絶えてしまいます。また厳しい冬や暑い夏との対決は、人間に農業や科学の発達を促します。このように生命と環境とは切っても切れない「縁」があるというのが仏法の見方です。
ではこの環境(国土)と生命の関係について、仏法ではどのように説き、大聖人はどのように展開しているのかを順を追って解説していきたいと思います。
【依と正の関係】
それでは「依正不二」を正しく把握するために、まずは「依」「正」「不二」それぞれの言葉を正確に理解していきたいと思います。
「依」は依報ともいい、十界の生命が生を営むための「依りどころ」という意味で、いわゆる自然環境や国土のことを指します。「正」は正報ともいい、十界の生命が生を営む一切の「衆生」という意味で、ここではとくに人間生命のことを指します。また依報・正報の「報」とは〝報い〟という意味で、私たちが生を営む上で行う善悪さまざまな行為は主体(正報)である私たちの生命に刻まれます。それが「因」となり、なにかの「縁」によって色心の上に「果報」となって現れます。それが「報」という意味です。
要するに、この報いを受ける主体(有情)の身心を「正報」といい、主体(身心)が拠りどころとする環境・国土を「依報」といいます。
大聖人は「すべての環境は依報であり客体である。衆生は正報であり主体である。たとえば、依報は影であり、正報は体である。身がなければ影はない。それと同じく正報がなければ依報もない。またその正報は依報をもってその体を作る」(瑞相御書、現代語訳)と仰せです。
この御文は、一切の環境(客体)は衆生(主体)によって動かされていく存在であり、衆生がいなければ環境(国土)というものはなく、またその衆生は環境によって形成されていくという意味ですが、この依正不二の原理を大聖人は実践面(事)のうえから「正報」こそが中心であることを示され、主体である私たちとそこに住む環境や国土は決して切り離して考えるべきではなく、もともと一体(不二)なのだと言われています。(※これについては後ほど詳しく掘り下げたいと思います。)
たとえば、太陽から降り注ぐ光のエネルギーも、大気も、すべて依報です。そこから光合成が行われて植物が生長する過程に依正の断絶がないように、私たちもその植物を食べて生命を維持し、いつのまにか依報たる植物が正報そのものになっています。
このように依報(植物)が正報(衆生)をつくるということは、依報と正報は決して断絶したものではないということを物語っています。この依報と正報が渾然一体(不二)となって自然と人間を統一的に把握するというのが仏法の見方です。自然は人間に働きかけ、人間は自然に働きかけます。その渾然一体となった姿そのものが「生命」の実体であり、それを究明したのが「依正不二」の法門です。
池田先生はこの関係性を糸にたとえて「生命の糸」と呼び、すべての生物はこの生命の糸を相互に張り巡らしながら、大自然のなかで生き、大自然と深く関わり合っていることを通して、地球を「一つの生命体」として認識すべきことを主張しています。
この主張はただ単純に〝自分というものと、環境というものとがあって、その二つが一体(不二)である〟という呑気な考え方で終わるのではなく、自分と環境とが互いに深く関わり合うことによって、ついには自分も環境も〝不二〟となって溶け込んでいる生命の姿を「覚知」(体得)することを目指していくのだ——と私たちに呼び掛けているような気がします。
【依正は妙法の当体】
次に、大聖人は「地獄界から仏界までの十界の依報と正報の当体はすべて妙法蓮華経の姿であり、依報があるならば必ずそこには正報が住している」(現代語訳、諸法実相抄)と言われています。
これは依報と正報は不二の関係であり、依正ともに妙法の当体であるという意味です。私たちと環境とは互いに独立した因子を持ちながら、強く影響し合っているように見えますが、この大聖人の「生命論」に従えば、その本質は「妙法」という一体の生命のうえに依報と正報という二つの現われ方をした差別相が生命の実体であると言えます。
ところが私たち人間は往々にして環境を固定化して考え、どうしても一定不変の環境に一切の生物が置かれていると思いがちです。とは言え、人間には人間の環境があり、鳥には鳥の、魚には魚の環境があります。また同じ人間であっても、人はそれぞれ違った環境や国土に住んでいます。正報たる生命の主体が無数であれば、依報たる環境もまた無数です。
しかし無数に存在する依報(環境)も正報(衆生)も元をたどれば同じ一つの〝源〟より出発していて、もともとは一体不二であるというのが大聖人の「人間観」です。では衆生と環境の根源たる実在(本質)とはいったい何かといえば、それが「宇宙生命」であり、これを大聖人は〝妙法蓮華経〟の姿であると説かれたのです。
妙法蓮華経についての意義は多岐にわたりますが、一面から簡単に説明すると、「妙法」とは正報たる生命の本源であり、「蓮華」とは非情の依報であり、「経」とは三世常住という意味で、妙法蓮華経全体で「宇宙生命の根源」を言い尽くしています。
先ほども言いましたが、依正不二の原理は認識論のうえでは本来、依報も正報も一体不二ですが、実践面においては「正報が体」「依報が影」であり、あくまでも「正報」が中心となります。すなわち大聖人の説く「依正不二」は、ただ単純に〝環境と人間は不二である〟という理屈で終わるのではなく、自己の変革(人間革命)は即依報(環境)の変革につながり、強き主体(正報)の確立こそが〝成仏への偉大な力〟となることを示されたものであると確信します。
【諸法実相の観点から】
少し話は変わりますが、爾前経は十界に差別を設けていましたが、法華経方便品の「諸法実相」によって十界互具が示され「万人成仏」の原理が説かれました。諸法実相をごく簡単に説明すると、十界の生命(個々の生命)ならびに森羅万象(個々の万象)の諸法が、ことごとく妙法蓮華経(実相)の当体であるという意味です。また「十如実相」ともいうように、諸法という空間的に広がる森羅万象のどれ一つをとっても、如是相から如是本末究竟等の十の如是を備える生命のありのままの姿(実相)が説かれています。森羅万象とは人間はもちろんのこと、宇宙や自然の一切の事物・現象が含まれます。
大聖人は「十界各々本有本覚の十如是なれば、地獄も仏界も一如なれば成仏決定するなり」(御義口伝)と言われ、十如実相の十界に対する意味を明快に示されました。
どういう意味かというと、爾前経では相互に断絶のあった十界の各界が、法華経ではその奥に「一如」として平等の「法」(十如是)を備えているという真実の世界を示したのです。つまり、十如実相は単純に十界の生命が平等だというのではなく、十界という差別の奥に「平等の本質」があり、それを覚知することが成仏のカギであるということを示したものです。
たとえば「A」という人と「B」という人とは、それぞれ独自の個性を持ち、差別のある存在です。しかし、AもBも同じ「人間」であると自覚すれば、互いに尊重しあう心が生まれ人間としての尊さが芽生えます。とは言え、同じ人間だからといってAさんとBさんの個性が消えるわけではありません。同じ「人間」であるということと「個性」があるということはまったく別次元の問題です。それと同じように、十界の差別と十如実相の意味するものとは、まったく別次元にあるという認識は非常に重要です。
その上で、すべての衆生が等しく仏に成り得るということは、成仏の道が特定の資格をもつ者だけに限られているのではなく、三悪道(地獄・餓鬼・畜生)の衆生であれ、三善道(修羅・人・天)の衆生であれ、二乗(声聞・縁覚)の衆生であれ、仏になるかならないかは、結局、すべての人の根底に開かれている宇宙万象(依報・正報)の根源の法(南無妙法蓮華経)を覚知(体得)するか否かにあるのではないかと考えます。
【主体性の確立と人間革命】
それでは先に紹介した御文「十方は依報なり、衆生は正報なり。依報は影のごとし、正報は体のごとし。身なくば影なし、正報なくば依報なし」 (瑞相御書)について、もう少し掘り下げて考えていきたいと思います。
人間には太陽のように明るく晴れ晴れとすみきった「法性」と呼ばれる生命状態と、悩みに押しつぶされて暗く沈んだ「無明」と呼ばれる生命状態の二つが共に備わっていて、その法性と無明を我が生命の中にとらえた変化相として見るのが、大聖人の人間観です。そして、自己の生命の中に「法性」が顕現したとき、「依報」である環境もその影がくっきりと映り、十界の変化相は環境にそのまま映し出されていくというのが「依正不二」の原理です。
たとえば、「餓鬼は恒河を火と見る、人は水と見る、天人は甘露と見る。水は一なれども、果報に随って別々なり」(曽谷入道殿御返事)と大聖人が言われているように、同じものを見ても見る人の果報(境涯)によって見え方は実に様々です。
しかしこの映り方には二通りあり、一つは自己の生命の実感として瞬間的に顕現される場合と、もう一つは時間的な流れのなかで自己(主体)の変化が次第に環境(客体)に顕現されていくという映り方です。
たとえば、同じ家に住んでいても願いが叶って歓喜しているときは、周りがどうであっても気にならないし、どこにいても幸せです。しかし絶望にうちひしがれているときは、何もかもが気に食わず、どこにいても何をしても地獄です。このように同じ環境であっても主体が感じる反応はさまざまです。
大聖人は「これほどの悦びをばわらえかし」(種々御振舞御書)、「流人なれども喜悦はかりなし」(諸法実相抄)、「日蓮が流罪は今生の小苦なればなげかしからず。後生には大楽をうくべければ大いに悦ばし」(開目抄)と叫ばれたもっとも深い歓喜の瞬間は、大聖人の人生においてもっとも過酷な「竜の口の頸の座」と島流しにあった「佐渡の地」でした。
また、戸田先生が法華経を悟達し、感動にうち震えたのは寒い「獄中」でした。戸田先生はそのとき、〝生命の底から湧き上がってくる歓喜は全身を包み込み、広々と果てしない境涯にあった〟(趣意)と後に語られています。このように生命の実感に即していえば、主体が「仏界」であれば、いかなる環境も即「仏土」です。
大聖人が「娑婆世界の中には日本国、日本国の中には相模(さがみ)国(のくに)、相模国の中には片瀬(かたせ)、片瀬の中には竜の口に日蓮が命をとどめおくことは、法華経の御故なれば、寂光土ともいうべきか」(四条金吾殿御消息)と言われたのはこのことを指しているのだと思います。
仏界の生命はいかなる環境にあってもそれに左右されることはありません。この依正不二の原理から「仏」と表現される〝人間性のもっとも清浄な生命〟〝躍動する生命〟を自分自身の中に開花させ、環境を支配しきっていける強固な主体を確立していくことが信仰の目的であり、重要な一つの「柱」になります。
今日皆さんに伝えたいことは、大聖人の仏法は民衆救済を願う生きた生命哲学であり宗教です。どんなに恵まれたすばらしい環境に居ても、悩みに押しつぶされていては不幸です。人生の充実感もなく、弱々しい浮き草のような惰性の毎日を送っているような人生とはきっぱり決別すべきです。たとえ地獄のような苦しみに苛まれることがあったとしても、「衆生所遊楽」の人生を歩んでいける「金剛の主体」を築き上げていくことを教えているのが大聖人の仏法です。
ゆえに全生命をもって題目をあげ抜き、実践を通して教学を五体に刻み込んで、自分のものに肉化しなければ信仰している意味がないと思うのです。
その基盤となる自己の人間革命の実践 (信行学)を忘れて、表面的な平和活動(選挙活動など)に従事したとしても本当の意味での「自身を変革した」ことにはなりません。
池田先生は『小説・人間革命』の冒頭で「一人の人間における偉大な人間革命は、やがて一国の宿命の転換をも成し遂げ、さらに全人類の宿命の転換をも可能にする」(第一巻)と記されています。これが「依正不二」の真髄であり、永遠に変わらない、また変えてはいけない「不滅の学会精神」であると確信します。
以上で終わります。